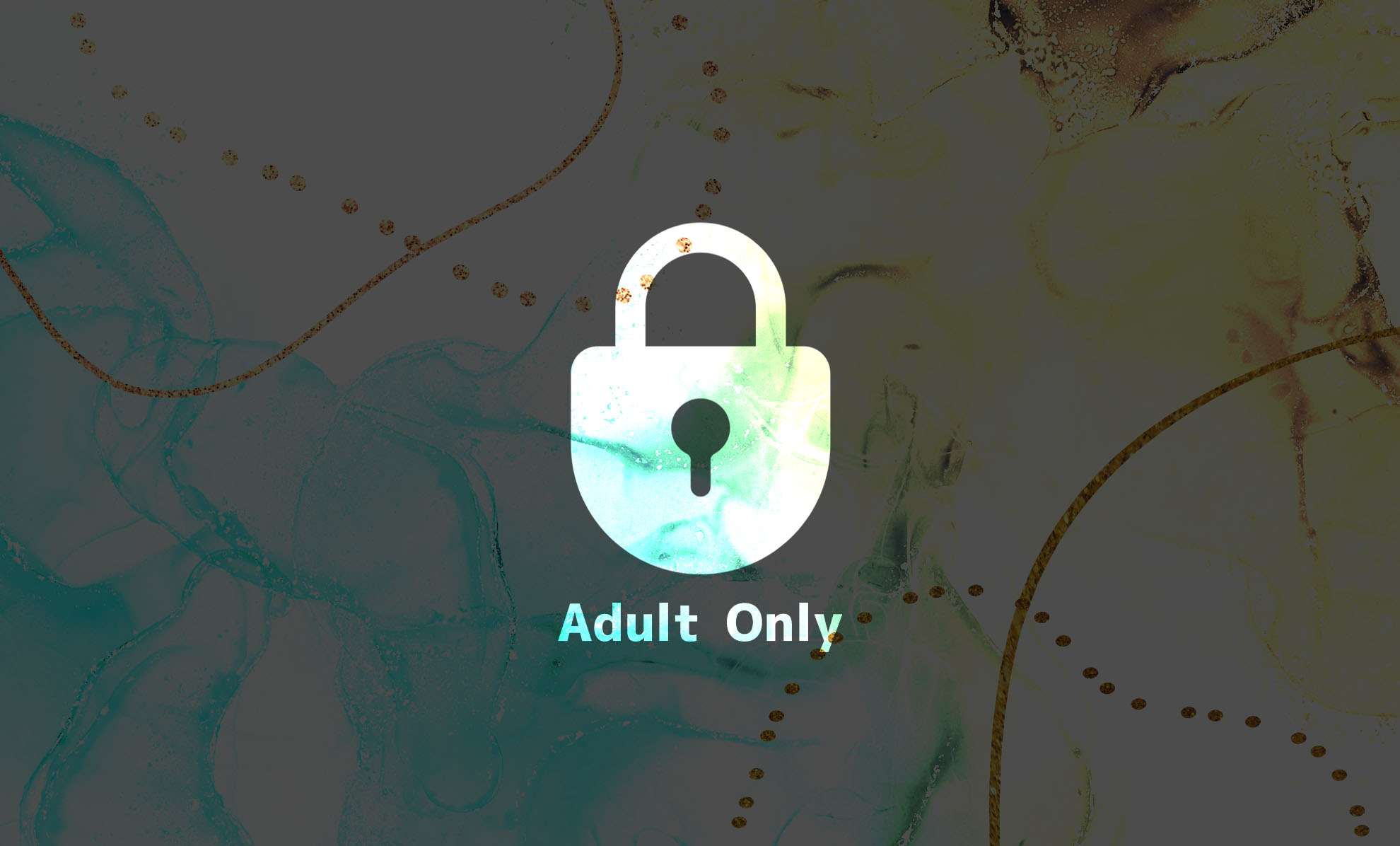璃月においては北国銀行を拠点として活動している以上、執行官のタルタリヤには銀行業務の仕事も当然ながら存在する。そして銀行が、経済が、金が忙しく動き回る時、それはタルタリヤの繁忙期となる。
事務仕事は必要である以上仕方ないと割り切っているけれど、やらずに済むなら越したことはない程度の認識をしている。なにせ事務仕事ばかりだと身体が鈍ってしまいかねないし、なによりタルタリヤは戦うことが好きなのだ。
その日、職場から解放されたのは夜も更け、璃月港も寝静まり始めるような頃だった。こんな真夜中ならそこらの酔漢と一試合、という欲望がちらりと心臓を炙ったが、欲求不満が過ぎたためにその程度では足りぬと一蹴した。そんなものはただの虐殺だ、タルタリヤが求める戦いではない。
月くらいしか光源のない街を進み、寝泊りしている部屋へ戻ったところまでは良かったのだ。べったりと身体に染み付く疲労を洗い流すように湯浴みを済ませ、寝台に転がってからが良くなかった。
熱が籠っている。確かに事務仕事と、こんな忙しい状況で舞い込んでくる緊急の仕事と、しかし暴れ散らすなんてもってのほかの顧客対応と、別にタルタリヤでなくとも出来るが最初から一番上の人間を出した方が手っ取り早い案件と。ここ最近はずっとそんな調子だったから、言ってしまえば仕事に精を出しすぎていたのだろうと思う。
――そういえば、会ってないな。
暴れたい、戦いたい。そう思いつつ、この身がファトゥス第十一位『公子』である限りは、ただただ自らの快楽のためだけにこの力を振りかざすわけにはいかない、という理性が確かにあった。それだけは救いだったが、どうしてその理性はもっとまともな仕事をしなかったのだろう、と後悔している。
「……っ、は、んん、ぅあ」
仕事に時間を費やしていたものだから、最近は鍾離と食事にも行っていなかったし、旅人ともあまり話せていなかった。それがより欲求不満に繋がっていて、それで。
とぷりと先走りを溢れさせる自らの屹立に指を絡めているが、一向に絶頂はやってこなかった。ああくそ、なんでこんなことに。柔く噛んでいた唇を舐める。どうしてこんなことになっているかなんて、そんなのは明白だ。
鍾離と会えていない。それだけだった。
元々性欲の類はさほど強いわけでもなく、欲らしい欲は戦闘で満たしてきた人生である。性行為の経験がなかったとは言わないが、それに溺れるタイプではなかった。戦闘の方が楽しかったからだ。だからきっと何かの間違いだと思いたくて堪らない。
「く、っそ……」
こんな真夜中に一人で自慰をしているだけならまだしも、物足りなくて達せないなんて信じられない。今までであれば、事務的に処理してさっさと眠りにつけていたはずなのに。仕事自体は今日でひと段落ついたから明日以降はもう少し余裕が出来るはずだが、これで寝坊や遅刻なんてしたら羞恥で死にたくなる。
にゅくにゅくと扱いて、親指の腹で先端を刺激して、確かに気持ち良いのに満足とは言いがたい。どうして。――なんでイけないんだ。ここまで来ると泣きたくなってしまう。はあッ、と湿っぽい息を吐き出して、タルタリヤは目を閉じた。
――ここが好きか。
不意に脳内で響いた声に、びくんと身体が跳ねる。涙が目尻に滲んだ。あの熱を孕んだ低音が耳元で囁くことを思い出しただけで体温が上がる。途端に咥内にあふれ出した唾液をこくりと飲み下した。
「ッ……♡ っ、は♡ ぁ……♡」
あの長く美しい指先が、この傷だらけの身体をなぞるさまを、瞼の裏に映し出す。途端に脳髄がびりびりと痺れだして、屹立を包んだ掌に力が籠った。自分では意図していなかった刺激に「ひ、」と引き攣れたような声が上がる。
唇の端から溢れそうになる唾液を何度も何度も飲みこんで、頬を伝い落ちる涙を肩で拭った。ああ、そうだ。なんで、なんて、最初から分かっている。
鍾離が足りなかった。戦闘で満たせない欲の満たし方を、あの男に教え込まれてしまったのだ。普段は晒されないあの美しい指先で丁寧に暴かれ、拓かれて、タルタリヤはあの男に身を委ねる快楽を、もう充分に思い知ってしまっていた。
「はーッ♡ はぁ、っん……ぅ……♡」
疼く腹の中を、ぐちゃぐちゃに突いて欲しい。ねっとりとした腰使いで焦らしてほしい。頭がおかしくなるくらいにたくさん、たくさん。
「――せん、せ」
先走りに塗れた指を後孔に伸ばす。つぷりと差し込んだ指は思ったよりもすんなりと飲み込まれて、そこまで暴かれ慣れてしまっていたのかと愕然とした。きゅう、と締め上げている指はタルタリヤのものでしかなく、鍾離がやる時とは感覚が違っている。とろんとした唾液が零れ、肌を伝った。
鍾離が良い。あの声が、あの指が、あの目が。僅かに膨れた場所を指で押し上げ、喉奥から込み上げる嬌声をどうにか留めた。確かに得られる快楽は似ているが、それだけだ。タルタリヤが欲しいのは鍾離が与えてくれるものであって、自ら慰め得られるものではなかった。
「ぅ、~~ッ♡ ……くそ、っひ、ん……くそ、も、やだ、ゃ……♡」
屈辱的だ、と思う。自慰さえままならなくなってしまった。全部鍾離のせいだ。けれど肉壁をぐちぐちと押し上げる指を止められもしなければ、瞼の裏に描いた鍾離を掻き消すことも出来なかった。
鍾離にそれを許したのは、間違いなくタルタリヤなのだから。
びゅる、と白濁を吐き出す。ちかちかとした明滅が収まるのを待って、タルタリヤはいつの間にか固く閉じていた瞼を押し上げた。腕で涙を拭い、手の甲で唾液も拭って、腹の上にぶちまけた白濁を見下ろす。
「……さいあく、だ……」
まだ腹の奥の疼きは止まず、そこを埋める熱を欲していた。仕事で根を詰めすぎると何かしらおかしくなるらしい。そういうことだと思いたかった。戦いを愛するがゆえに、タルタリヤは戦えなさ過ぎるとこうってしまうのだ。――いや、それはそれで問題がないだろうか。
余計な思考を払うように首を横に振って、タルタリヤは溜め息を吐いた。
「……せんせえ、」
恋しくて堪らないなどと、家族以外に思う日が来るなんて考えもしなかった。
//
「手合わせしてくれない?」
苛立ちを隠しきれていないタルタリヤが出会い頭に言い放った誘い文句に、珍しく鍾離が頷いてくれたのは何故だったのだろう。今となっては分からないが、滅多に付き合ってくれない鍾離との手合わせは本当に楽しかった。
ざくりと地面に突き立てられた槍は、仰向けに倒れたタルタリヤの耳のすぐ横にあった。見下ろしてくる男を見て湧き上がってくるのが、一人では発散しきれなかった熱なのだから救いようがない。悔しいとも思えないようなくらい、今日のタルタリヤの動きは良くなかった。
これまで手合わせしてもらった時も「狙いが正確だからこそ分かり易い」と度々鍾離に言われたが、今日はそれよりも酷かったという自覚がある。動きも直線的だったし、最早必死だったから手数は多かったが、鍾離にとってはがむしゃらでしかない動きだっただろう。
フェイクだってろくに入れられなかった。これまでの手合わせの中では最悪の動きであり、最悪の結果だ。戦っている時間ははっきりとは分からないけれど、もしかすれば最短だったのではないだろうか。タルタリヤは格好悪かった。自分でも分かるくらいにはそうだったが、鍾離は。
怜悧な目元は戦いの只中であればあるほど鋭く状況を観察する。タルタリヤと手合わせしている鍾離もそうだった。その鋭い黄金色が好きなのだ。どうすればこの男の不意を突けるのか、この男から一本取れるのか。考えて、試行して、鍾離がどう返してくるのかを、タルタリヤはそれをどう捌くかを考えるのが、そうして身体を動かすのが好きで堪らない。
今日は信じられないくらいの惨敗だったが、身体がぞくぞくして仕方ない。はあ、と息を零せば、起き上がろうとしないタルタリヤをじっと見つめている鍾離は目を細めた。
「今日は随分と――熱烈だったな」
「……せんせ、」
せっかく応えてくれたのだから、もっと万全の状態で戦いたかった。そんな気持ちもあるし、今度こそコンディションが整った時に鍾離に頷かせて見せるとも思っているが、それは今のタルタリヤには必要ない思考だ。
目の前に鍾離が居る。タルタリヤを見つめている。水元素で作り上げた双剣を空に溶かして、タルタリヤは鍾離に対して両手を伸ばした。
「ぐちゃぐちゃに抱いてくれ」
ここでいいから、とねだるタルタリヤを「余計なことを考えたくないからな」と言いくるめて璃月港まで戻ってきた鍾離は、そのままタルタリヤを自分の暮らす部屋に連れ込んだ。
戸を閉めた瞬間、散々焦らされたタルタリヤが鍾離に口付けるよりも先に、鍾離はタルタリヤを寝台まで引き摺って普段なら絶対やらないくらいに荒っぽく押し倒した。それなりに順序だてて事に及ぶ鍾離にしては珍しい性急さに、タルタリヤの熱は更に昂る。
もう何度も脱がされたことのある服を乱す鍾離の手を捕まえて、タルタリヤはその黒い手袋を口でずるりと脱がせた。現れた掌に口付けて鍾離を見れば、鍾離は噛み付くようにタルタリヤの唇を奪う。
「っ」
「んんッ……♡ ふ、ぅ♡」
咥内に侵入してきた舌に自分の舌を絡め取られ、タルタリヤは息苦しさに涙が滲んだ。それにさえ甘い痺れを感じてしまう。鍾離の背から滑り落ちてきたのだろう、頬を擽る鍾離の髪が更にタルタリヤの神経を鋭敏にさせた。
鍾離の髪留めを引き抜けば、艶やかな髪がタルタリヤの視界を遮る。狭くなった視界の中で、ぎらつく金色が際立っていた。
「公子殿は」
「は、っ♡ ……ん、なに? っん♡」
「煽るのが上手くなったな」
「っに、それ、ッひ♡ ほ、めてんの?」
「褒め言葉だ。……俺だけに留めていて欲しいが」
「あっぁ♡ ぅ、」
キスの最中にストールは剥ぎ取られ、ジャケットの前部分は開け放たれていた。伝い落ちた唾液を舐め取るように首筋に唇を寄せてぼそりと呟いた鍾離に、タルタリヤは反論しようとしたがそれより先に嬌声が口を突く。
首筋に柔く歯を立てられるのに弱いのは、そこが急所だからだ。噛み殺されてしまったら、と不穏を愛する己が目を覚ます直前で留まる歯は、タルタリヤの皮膚を噛み千切ろうとはしない。それは愛撫であって攻撃ではないから、タルタリヤはされるがままになってしまう。
加減の上手い男だ、と思う。こんなにもタルタリヤを好き勝手できるなら、タルタリヤが一人でも困らないくらいに留めていてくれれば良かったのに。途端にあの夜の悔しさが返り咲いて、タルタリヤは嬌声ばかりを吐き出す自分の唇を噛んだ。
「っ、ッ……~~っ♡」
「……公子殿、声を」
「――~~っ、ぅ」
「……強情だな」
顔を上げた鍾離はべろりとタルタリヤの唇を舐め、まるごと覆うように口付ける。しつこく唇を舐めてくる鍾離に噛む力が抜けてきたところで、不埒な指がタルタリヤの胸に触れた。ぴんと立ち上がった尖りの傍をそっとなぞられるだけでくぐもった声が漏れる。
焦らすように周りを指先でくすぐり、胸筋の形に手を沿わせて柔く揉み、かと思えばその手はそっと腹筋へと下っていく。鍾離の愛撫ひとつひとつに身体を震わせてしまうタルタリヤにとってはたまったものではない。
「っふ、~~ッ! ふうっ、ぅ、あッ?!」
「はは、」
「ぁ、っばか♡ ひんっ♡」
「気持ちいいだろう?」
「ぅあっ、ぁ、ぃ♡ いい、けど、」
きゅ、と尖りを摘み上げられた瞬間に離れていった唇を追いたかったが、鍾離の手によって与えられる快楽のせいで力が入らず、その唇を引き止めることは出来なかった。ぼろぼろと涙が零れる。
帳のように垂れる鍾離の髪に指を絡め、琥珀のように明るい色の毛先に口付けた。金珀が丸くなるのを見て、ふ、とタルタリヤは笑みを零す。
「ぐちゃぐちゃに、って、言っただろ……」
ゆっくりと丁寧に進められるのも良いが、タルタリヤの熱はずっと燻ったままなのだ。一回では到底足りないのだから、焦らされるのは全部暴かれてからが良い。その熱を埋められ慣れた腹が切なく疼いて、寂しくて仕方ないから。
手袋を嵌めたままの方の鍾離の手がタルタリヤの頬に添えられた。その手袋も片手と同じように外してやれば、鍾離はタルタリヤを褒めるように頬を撫でる。その柔らかな手つきに目を細めると、形の良い唇がタルタリヤの耳に寄せられた。
「好きにしても?」
湿った吐息に混じり、ざらりとした低音が響く。びりびりと腰が痺れて、タルタリヤは足の指先で敷布を握った。誘った側ではあるが、その問いにまで素直に答えるのはなんとなく嫌で、そのほのかに汗ばんだ頬に口付ける。
じ、と鋭い黄金色がタルタリヤを見た。
「……ん」
答えなければ動かないのだろう。早々に悟って、タルタリヤは首筋が熱くなるのを感じながらも小さく頷いた。瞬間、ゆるりと綻んだ目元を見てしまい、タルタリヤはぐっと唇を噛む。咎めるように唇をなぞる指に噛み付いた。鍾離が口元を歪める。
言わなくても悟れ、というのはさすがのタルタリヤも少々理不尽だと思っているし、それで妙な方向に勘違いされても困るから言うつもりはないけれど。
「――こんな風に誘うの、アンタにしか、しない」
見境なく誘いをかけるような男に思われているのだけは心外だった。嬌声に阻まれて言えなかったことを口にして、ふい、と顔を背ける。
「ハ、っふ……そうか」
「ッ! ぁ、せ、せんせ、っ♡」
「ぐちゃぐちゃに、だったな」
タルタリヤの身体を指でなぞりながら、男はうっとりと微笑んだ。
ぎゅう、と締め付けられたのは、腹の奥か――それとも。
2020.12.30