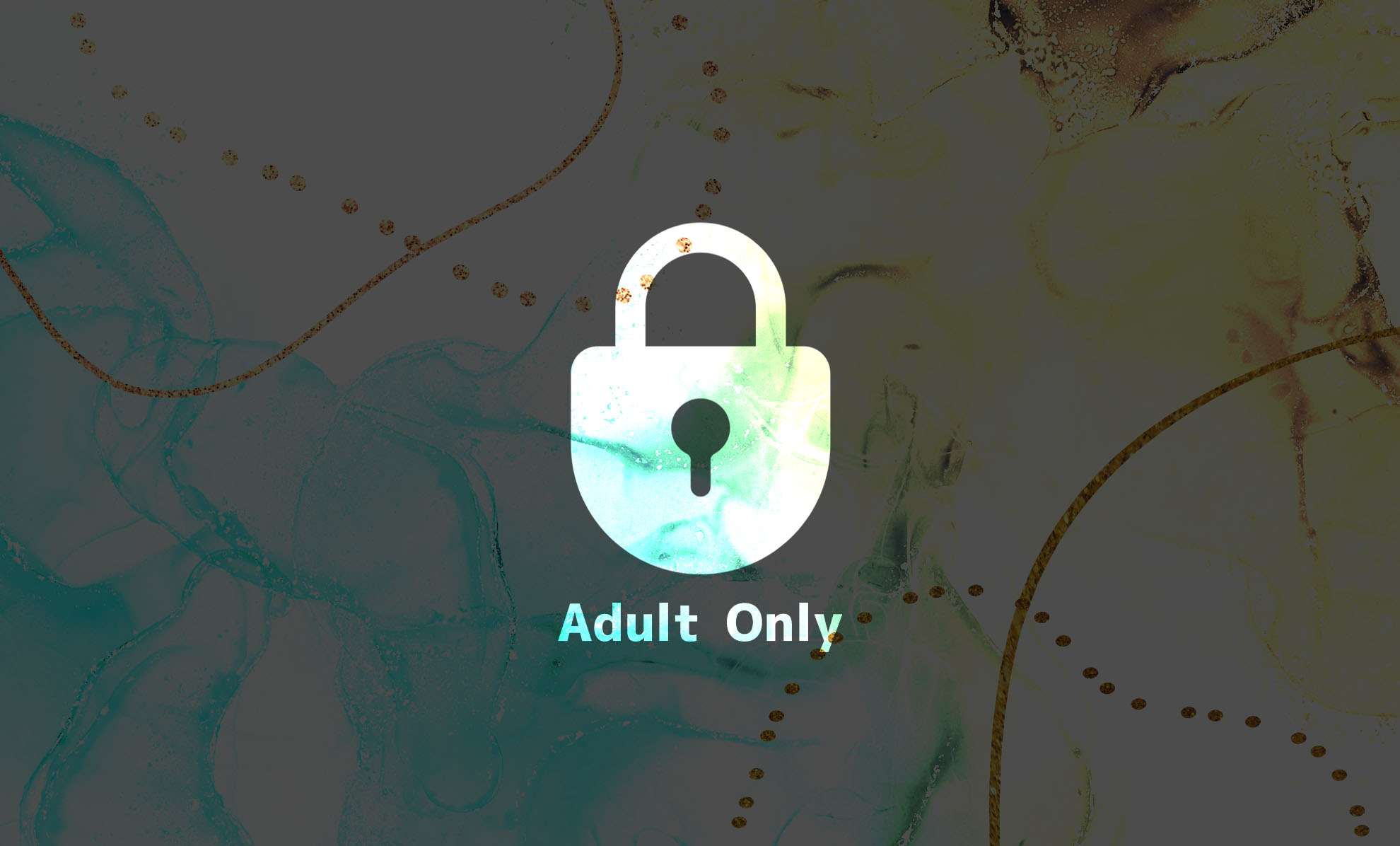一礼して部屋から静かに出て行った部下の背を見送り、タルタリヤは手の内にある銀色の薄っぺらい金属板を弄んだ。チェーンを通す穴の空いた金属板にはつらつらと文字が刻印されている。
Имя、рождения、пол。
既にチェーンはなく、タルタリヤの手元にあるのは金属板だけだ。力を込めて曲げようと思えば曲がってしまうような、ただの板。掌で握って隠せてしまうこんなちっぽけなものが、証明になるのだ。
これは一人の人間が生きた証だ。生きていた証だ。
本人の手元を離れた時点で――持ち主の死は確定しているが。
刻まれた名前を知っている。その名を呼んだことがある。報告書でも見た名を、今度はタルタリヤが記して、本国へと送らなければならない。掌で、指で、金属板を弄ぶ。きら、と明かりを反射して鈍く光る板は無機質だった。
この金属板は報告書と共に本国へ送られ、遺族のもとへと届けられる。
遺体は幸運にも形を留めていたが、さすがに航路だろうと身体ごと運ぶのは困難だ。近場であれば氷元素を操れる者が遺体の腐敗を防ぎながら運ぶこともあるが、ここは璃月である。遠くで死ねば、二度と祖国へ帰れない。
だからそのぶん、名を、持ち物を、せめてものしるしを帰すことで、僅かながらも慰めとするのだ。
「はあ――……」
報告を聞いた段階で――報告を持ってきた部下の様子を見たところから、分かっていた。部下を一人死なせ、生き残った部下は成果を持ち帰ったが負傷していた。タルタリヤの指示は最善手ではなかったことの証左である。
部下たちの能力を過信していた。敵の強さを見誤っていた。どちらであれそれはタルタリヤの落ち度で、失策だ。他の誰の目もない執務室で一人、そっと腰掛けていた椅子の背凭れに身体を預けた。
ゆるり、と身体から力を抜き、金属板を握りこんだままの拳を額に当てる。
命は命であり、そこに貴賎はない。殺し合いが好きなタルタリヤではあるが、だからといって死そのものを軽く扱おうという気はなかった。誰のものであれ、何のものであれ、命は命である。
戦場では当然のように命が散る。戦うことが仕事の一つに組み込まれている以上、命を落とす危険性はいつだって存在していた。それは部下も、執行官であるタルタリヤとて違いない。明日と言わず今日死ぬ可能性だってある。死はいつもそこに在る。
だとしても――少なくとも、タルタリヤ自身も先ほど姿をしっかりと確認してきた、まだ顔が判別できる程度の損傷だった部下の死は、部下の弱さそのものが原因ではないのだ。
ぼんやりと天井を眺める。璃月の建築様式に則った建物に、スネージナヤらしさは微塵もない。金属板を取り落とさないようにそっと拳を解いて、掌のうちのそれを見た。鈍い銀色。無彩色のそれは、雪に埋もれた祖国の静けさを思わせる。
「……」
刻印された名前を呟く。死に顔を脳裏に映し出す。
遺族でもない、ただの上司に過ぎないタルタリヤに残されるものはない。精々が本国に送られる、部下が命を落としたのが璃月であるということと、その時璃月に居た執行官がタルタリヤであったという記録だけだ。そのほかに形などありはしない。
重さなんて微塵も感じられない薄っぺらな銀色を執務机に置いた。ただの封筒に手紙と共に入れたところで邪魔にさえならない、こんなもの一つが、死んだ部下が確かに居たことの証明になる。
もう一度名前を呟いた。
「――難しいな」
死した相手にかけるべき言葉は、ずっと分からないままだ。
//
ファデュイの悪評は付き纏う。別にもう慣れてしまっているけれど、やはり何も気にせずに話そうと思うと個室のある店を選んでしまうのも癖だった。新月軒だろうと瑠璃亭だろうと、高級料亭と呼ばれる場所での支払いはいつだってタルタリヤ持ちだ。
海産物に苦手なものが多い鍾離に合わせた、瑠璃亭での宴席はもう何度目か分からなかった。目の前で上品に食事を進める男に聞けば正確な数が返ってくるだろうが、知りたいとも思わなかったし、きっとタルタリヤは数えないでいた方が良い。
「鍾離先生は往生堂の客卿なわけだろう」
「そうだな」
「仙人を送る儀式が得意だから、往生堂に籍を置いてるの?」
得意というよりは、最早忘れ去られた細々とした部分まで記憶しているから、適任というと鍾離のほかに居ないというのが正しいのだろうけれど。タルタリヤの唐突な問いに鍾離は疑問符を浮かべるでもなく、そっと箸を置いてタルタリヤに向き合った。
皿はもうほとんど綺麗になってしまっていて、後は食後の茶をゆっくり飲んだら解散になるだろう。気分ではなかったからという理由で、今日のタルタリヤは酒を頼まなかった。
そんな状態で、まるでこの時間を引き伸ばすかのような話題の振り方はあまり宜しくないものだっただろう。それでも、思えば一度も聞いたことのない話が思い浮かんだものだったから、聞いてみたくなったのだ。
「往生堂には代々世話になっていてな」
「じゃあ往生堂の……少なくとも堂主さんは、先生が凡人じゃないのを分かってたわけか」
「人の世に仙人が混じっていることはそう珍しくない。月海亭では半人半仙の者も働いているし、それ以外にも気付かれないようにひっそりと璃月で人間の暮らしを見守っている者は居るからな」
「まあ、まさかそれが岩王帝君だと思うかどうかは人による、か」
「伝説に残る岩王帝君は姿かたちが様々だからな。それに、長らく見た目が変わらない男が一人居ようと――元より往生堂は人々の生活の陰に存在している。気にかける者が少ないから好都合だったんだ」
その仕事柄、妖魔の類も引き寄せやすい、とは鍾離から聞いた話だ。
タルタリヤには想像しにくかったが、各地の遺跡の調査結果に目を通している中で幽霊を見たという記述もあったし、自分でも禁忌滅却の札で魔神を呼び起こした。こんな街中だろうと人外が現れても不思議ではないのは納得できる。
けれど件の堂主と鍾離が会話している様子をちらりと見たことがあるタルタリヤにとっては、鍾離の今の口ぶりが少々面白く感じられてしまった。
「長らく関わってきた往生堂だから無碍にも出来ない、って事情もあるのかな」
「……公子殿が何を考えたか聞くつもりはないが。仙人を送る俺に対して、彼女は人を送ることを専門としている」
「うん、それは少し聞いた覚えがあるね」
「俺が往生堂の客卿となることを選んだのは、それもあるな」
「なるほど」
遠からず送仙儀式が行われることを、狂言自殺を仕組んだ張本人である鍾離だけは分かっていたのだ。自分で自分の葬儀を執り行う気持ちがどういう気持ちか知らないが、ある意味では往生堂に対する鍾離なりの気遣いもあったのかもしれない。
茶を飲みつつ、タルタリヤはポケットに突っ込んできたもののことを思い出していた。
送る先はないし、だからといって捨てようにも処分に困って、結局数少ない荷物の中に放り込んで数年間そのままにしていたものだ。今更その存在を思い出した理由は明白だが、わざわざ持ってきた自分の行動の意味はあまりよく分かっていなかった。
「――往生堂と言えば」
「うん?」
「ファデュイからの依頼があったな」
「……なんだ、先生も知ってたんだ」
取引相手である北国銀行ではなく、ファデュイの方を口にしたということは、つまりそういうことだ。また全部お見通しか、とタルタリヤは溜め息を吐く。
葬儀を任せられる相手が取引先にあるのだから、頼らない手はないのである。璃月で死んだ者は往生堂が送り出す。少なくとも北国銀行と往生堂の取引が続く限り、よほど隠蔽する理由でもなければ。
金珀の瞳はタルタリヤをちらりと見て、手元の茶碗へと戻された。話すも話さないもタルタリヤ次第である。この男は分かりやすく強いることをしない。本気で求めれば求めるほど、他の誰にも悟られぬように根回しをする男である。
それほど珍しい話でもなかった。もう何度も経験してきたことだ。
「アビスの魔術師にやられてね。元々はただの偵察のつもりで俺が指示したんだけど、気付かれて戦闘に縺れ込んで、ってのが顛末」
「公子殿は直接出向かなかったのか」
「ちょうど別の取引先との接待の予定があったんだ」
戦える機会があるならそれに喜んで飛びつく犬のようにでも思われているのだろうか。鍾離の顔を見たが、別にそういう思いはなさそうだった。まあ、否定できるかと言われると微妙なところではある。
博士が残してそのままになっている、例の研究所でのことだった。
遺跡守衛の大半はあの時、旅人とタルタリヤで壊して再起不能に追い込んではいたものの、あれらを直されてアビス側の戦力にされるわけにはいかない。とはいえ研究所ごと壊すにも、万が一にも博士の残したものがあって不利になるのはファデュイの方である。
アビスが出入りし始めたという報告を受けたタルタリヤは、アビスが研究所内で何をしているかの調査をするためにも、内部の偵察を指示した。
結果、偵察隊に気付いたアビスと、生き残っていたらしい遺跡守衛と戦闘。偵察ということで人数も少なかったものの、アビスと遺跡守衛ともに行動不能にした上で、アビスはある程度情報を吐かせて処分。生き残った偵察隊は、アビスが残した文書を持ち帰った。
「部下たちは間違いなく強かったし、偵察だけ、あるいは戦闘になってもしっかり戻ってこられるような実力のある者を選んだつもりだった」
「その結果が殉職一名か」
「俺の采配ミスだね」
博士の残した研究所にはタルタリヤも一度、直接足を踏み入れている。だからこその指示だったが、だからこその油断でもあっただろう。溜め息は茶と共に飲み下し、タルタリヤはどうしてか持ってきてしまった、チェーンが通ったままの薄っぺらな金属板をポケットから取り出した。
空になった茶碗を卓に置いて椅子から立ち上がり、手中のそれを鍾離に対して放り投げた。
「っ、公子殿? これは」
「認識票。昔使ってたやつだし、もう俺が持ってる理由もないんだよ」
「何のつもりだ」
「なにも。じゃ、またね、先生」
スネージナヤの兵士であることの証明であり、例え死体がぐちゃぐちゃになっていようと個人を特定でき、死体を持ち帰れずともそれが死の証明になるものだ。ファデュイであれば誰もが、自分の名前や生年月日、所属が刻印されたそれを持っている。
女皇によって選ばれた、十一人を除いては。
鍾離に背を向け、ひらひらと手を振った。個室を出るために扉へと向かう。
兵士になった段階で与えられる金属板は、所属が変われば刻印し直したものと交換する形で、常に今の自分の情報が刻まれたものを持つことになる。
けれど――タルタリヤは自身の認識票を持っていなかった。
手元にあったのはかつての自分の名前と、かつての自分の所属が刻まれたそれだけである。過去の記録が刻まれた金属板は本当に無意味でしかなく、タルタリヤは生きている以上こんなものを家族に送るのも違う気がして、荷物に放り込んで長年そのままだった。
扉に手をかけたところで、後ろから肩を掴まれる。その手の握力がタルタリヤを逃がす気はないのだと告げていて、それでも振り返ろうという気にはならなかった。
「公子殿、何のつもりだ」
「意味なんかないよ」
「答える気はないのか」
「逆に聞くけど、そんなに知りたい話?」
ただの気まぐれで済ませてしまえば、考える必要もなくて楽だろう。タルタリヤの気まぐれなど今に始まったことではないのだから。ふと影が差す。
「贈り物には無粋だと思わないか」
「……それを贈り物だと捉えられる感性はどうかと思うけど」
「せめて自分の名前を刻んでおいてほしいものだ」
「俺の名前が刻んであったらあげてないよ」
それに今とは違うだけで、鍾離に投げて渡した金属板に刻まれた名とて、確かにタルタリヤのものであったのだ。鍾離には言ったことがないから、きっと知る由もないと思うが。
諦めて後ろを振り返ると、タルタリヤが思っていたよりも鍾離は真剣な顔をしていた。
言葉を失ったタルタリヤに、鍾離は静かに唇を寄せる。
「一人で帰るのか」
「……もっと上手い誘い文句ないの?」
「ふ、手厳しい」
//
素手の鍾離がタルタリヤの身体をなぞる。数々の傷が刻まれている肉体は、均整のとれた身体を持つ鍾離とは比べ物にならない。跡になって凸凹している場所に触れられるのはあまり得意ではなかった。
戦った証がみっともないとか、情けないとか、そんな風には思わない。これはタルタリヤが激戦を生き抜いた証だ。死に瀕しながらも、確かにそれに打ち勝ってきた歴史である。けれど元は武神たる男に触れられると、また別の感慨を抱きそうになるから嫌なのだ。
それに単純に他の部分よりも皮膚が薄いから感覚が鋭敏だという理由もある。どちらにせよ、タルタリヤは鍾離のそういう手つきが好きではなかった。
「先生、さ……焦らすの、好きだよね。趣味悪いよ」
「品なく食い散らかされるのが好みか?」
「ッあぐ、見えるとこは勘弁、っしてくれないかな……!」
「つけてはいないさ。ファデュイの公子は性にだらしない、なんて噂が流れるようなことはあるまい」
一度軽く噛み付いた後にちゅ、と首筋に口付けながら言われたところで、あまり説得力はない。タルタリヤはここ璃月において鍾離以外と寝ていないが、逆に鍾離に弱みを握られていると同義なのだから。
しないと言えばしない男ではあるけれど、タルタリヤが思うよりもずっと強かで策士で、地道な根回しを疎ましく思わないタイプなのだ。ああくそ、と悪態をつきたい気持ちを抑え、後孔に伸びてきた指の感覚に奥歯を噛み締めた。
潤滑油に塗れた指の侵入は、何度身体を重ねようと慣れない。ぐうるりと縁の辺りを広げるように指を回される感覚に、無意識に詰めていた息を吐き出す。慣らしている方とは別の手は、未だに傷跡に触れていた。
「俺の傷跡、」
閨事の最中にあまり積極的に口を開きたいわけではないけれど、まるで可愛がられているみたいな手つきが落ち着かなくて、それを認識する頭をどうにか誤魔化したくて、苦し紛れに言葉を投げかける。
鍾離はじ、とその金珀でタルタリヤの目を見つめた。そんな真面目腐った顔をしながら情事に勤しまないでほしい。もっと熱で浮かされていたら、まだ。
込み上げる感情と、変わらず動かされ続けている胎の中の指の感覚を堪えつつ、タルタリヤは鍾離から目を逸らす。ベッドサイドにある手袋や指輪などのアクセサリーに混ざって置かれている、自ら外した仮面が視界の端でちらついた。
「そんなさわるほど、目立つ?」
「……目立つか目立たないかで言えば、傷だらけだからな。数の多さに面食らう者は多いだろうが、戦士の肉体だと思えば納得も出来る」
「んぅっ……じゃあ、ぅ、はあ、なんでそんな、しつこく触るの――ッ、ひ」
これまで散々弄繰り回されて立派な性感帯となった場所を、長い指がとんとんと刺激する。それだけで声が裏返るのだから、タルタリヤの身体は鍾離の良いようにされすぎていた。鍾離の唇が頬に落とされる。
離れるかと思えば、今度は唇の端に。前立腺の傍を焦らすようになぞって、また前立腺に触れて、を繰り返されているタルタリヤの口はろくな音を出さず、呼吸は荒くなるばかりだ。どうせなら塞げよと、タルタリヤの方から鍾離の唇を奪った。
睫毛さえ触れ合いそうな位置に鍾離の瞳がある。岩元素の神の目よりも深みがあって、石珀よりも金属めいていて、その眼差しですべてをあかしてしまいそうな、それでいて淡々と見守るだけでいるような、どこか無機質な色をしている。
敷布を握り締めていた手を持ち上げ、口付けたままその目元を覆い隠した。
「ふ……う、っん」
「んんッ、ぁ、はふ、ん、ん……!」
咥内をまさぐる舌は長く、酷く器用に動く。ちぅ、と可愛げのある音を立てて吸い上げられるだけでじゅわりと唾液が溢れるようにされてしまった身体には、口付けひとつだって毒のようだ。
いつの間にか目元を覆っていた手は剥がされ、後孔をほぐしていた指は引き抜かれた。こくりと二人ぶんの唾液を飲み下して、タルタリヤはうつくしいかたちをしている男を見上げる。
その身体に傷はない。市井に混じって暮らすために準備したのだろう形だからか、元は神であったものだからか、完成された武人のなりをしていた。ただ生々しい傷跡がないことだけが、この男から武人らしさを消し去っている。
ひたりとほぐした場所に宛がわれた熱を察して、タルタリヤはそっと自らの太腿を掴んで足を開いた。
ふ、と鍾離が吐息で笑う。入り込む熱を締め付けそうになる胎をどうにか宥めすかして、タルタリヤは呼吸に専念した。この割り入られる苦しみの逃がし方にも、随分と慣れてしまったように思う。
「ぅ――っは、ぁ……、っふ」
「少し待つぞ」
「ん、そうしてくれると……助かる……」
目尻に滲んでいた涙をすくう指に擦り寄って、タルタリヤは深呼吸した。鍾離は余計に刺激しないようにだろう、タルタリヤの頬を撫でる以外に動こうとしていない。何度やろうと最初のうちはこうだが、いずれこのひと時さえなくなってしまうのだろうか。
自分の身体が順応していくことを喜ぶべきか恐れるべきか分からなかった。ただ少なくとも、それで一番得をするのは鍾離の方だろう。さすがに彼の欲そのものを胎のうちに抱いている現状、我慢を強いていることくらいは言われなくとも分かる。
「傷に触れる理由、だったか」
「っ、え?」
「まだ答えていなかっただろう」
「答える気、一応あったんだ……?」
煙に巻かれてしまうことに慣れていたものだから、鍾離にまともな返答をする気があったことに驚いてしまった。心外だ、と言わんばかりに唇を引き結んだ鍾離を見て、ごめん、と両手を伸ばす。
意図を察して上体を折るようにタルタリヤと距離を詰めた鍾離の、項の後ろで両手を組んだ。鍾離が近づく際に僅かに内部に更に深入りされるが、どうせこの後良いようにされるのだ。少しばかり詰まった息をゆるりと吐き出し、タルタリヤは鍾離と額を合わせる。
「それで、なんで触るのか言ってくれるの?」
「大層な理由があるわけでもないが。これは公子殿がこれまで戦い抜いて、生きてきた証だろう」
「……まあ、不覚を取った証でもあるけど」
「未熟な時代は誰にでもあるものだろう」
自分は傷一つ持たぬくせによく言うものだ。そんな悪態が口を突きかけて、タルタリヤは黄金色の瞳から目を逸らした。まるで名誉みたいな言い方をする。鍾離の知らないタルタリヤをなぞるための手つきだったとでも言うのだろうか。
それにしてはねちっこくて――すり、とまた傷が刻まれた場所を撫でた手に、溢れそうになった吐息を押し留めるように唇を噛んだ。
「そ、んな、いいもんじゃないよ」
「公子殿」
「ッふぅ、あっ、う……しつこいんだよ、せんせ」
「好さそうだが……そろそろ動いても?」
「ほんっと悪趣味だ……はぁ、もう……」
これまでの自分の行いを褒めてほしいとか、強さを讃えてほしいとか、そんな気持ちは一切ないというのに、自分の軌跡をなぞられることに喜びを覚えてしまったことを認めたくない。
いいよ、の一言さえくれてやろうという気にならなくて、鍾離の腰にそっと足を絡めることで答えにした。鍾離が面白そうに笑う。金珀の瞳はいつの間にかじりじりと燃える燭のように熱を帯びていた。
笑みを刷いた鍾離の唇が耳に触れ、低音を吹き込む。
「愛いな」
「~~ッ悪趣味! っあ、ぁふ、っ……ん、ァ、っ」
唇を耳から離さないまま、鍾離が動き出す。拓かれることに慣れた身体は鍾離の動きに素直に反応を返してしまうのが嫌だった。鼻にかかった嬌声を漏らしながら、鍾離の項の辺りで組んだ両手にひしりと力を込める。
腰から甘い痺れが駆け上って全身に広がっていく。前立腺もその奥も、まとめて押し潰されて、引き抜かれてはまた戻る。ただの出し入れだと言えばそれまでだが、そんな簡単な動きに溶かされているというのだから救いようがなかった。
鍾離の唇から漏れる吐息が耳に触れる。胎からだけでなく耳からも熱を流し込まれているようで、ぽろぽろと涙が零れ落ちた。脳髄ごとぐちゃぐちゃに乱されている。我を失っていく感覚は恐ろしいほど甘美だ。
ぎゅう、と締め付ける肉壁に構わず律動を続ける鍾離にしがみ付いたまま、タルタリヤはいつの間にか目を閉じていた。突き上げられるごとに息が詰まる。まともな呼吸が出来なくて、噤んでいた唇が緩んだ。
「っ――……あ、っうう、ぁ、あ、」
「ふ、」
「ひう、ッ耳、ゃ、ぁあっ」
吐息を流し込むばかりだった鍾離の唇が耳の外殻を食む。ぬるりとした熱く湿った感覚に思わず離れようとして、鍾離の手がタルタリヤの頭を固定する方が早かった。唾液で濡れた舌がねっとりと耳を舐め上げる。
腰と耳がびりびりして、頭の中がちかちかした。何がなんだか分からなくなってきて、身体の使い方さえ忘れてしまう。ぴんと伸びたつま先で敷布を蹴った。太腿で鍾離を挟んでも鍾離は止まってくれなくて、喉の奥から飛び出す甘ったるい声は更に高くなる。
心のどこかで握り締めていたはずの意地が、ついにタルタリヤの手を離れた。
「ぃ、っ――いく、ぃく、きもちぃ、いくから……っ!」
「ああ、そのまま」
「うぅうっあ、ぁ、ひ、ッ~~……」
がくんと堕ちる感覚がして、気付けばベッドに身体を沈めたまま、ただ荒い呼吸を繰り返していた。
明滅の収まった視界はぼやけている。瞬きを繰り返せば、余計な水分は涙として頬を滑り落ちていった。頬に朱色を滲ませた鍾離が呼吸のためか口を薄らと開けたまま、タルタリヤの頬を拭う。
くらくらした酩酊感のようなものが抜け切らなくて、ぼんやりと鍾離の顔を見上げた。そっと近づいたかと思えば、子どもにするような柔らかな口づけが額に降る。
「……今日は随分深く酔っているようだな」
「そ、かな……そうかも」
「一度抜くぞ」
「ん……ッ、はぁ。なんだろ、すごい、地に足着いてない、みたいなかんじだ」
「……終わりにしておくか?」
「やだ」
括られたままだった鍾離の髪から髪留めを引き抜いて、タルタリヤは寝台に肘を突いて僅かに上体を起こした。鍾離の唇に触れるだけのキスをして、まだなんとなくぼやけている気がする視界のまま鍾離の目に目を合わせる。
細められた目はタルタリヤの様子を観察しているらしかった。そう心配されるようなことはないはずだ。酒もなしにこうなるとは自分でも予想外だったが、一体何が原因だったのだろう。
「公子殿は耳も弱いのか」
「知らないよ。先生のが詳しいんじゃない?」
「もう少し言葉に気をつけた方が良いぞ」
「……元気だね」
「続けるんだろう」
内腿に擦り付けられた鍾離のそれは芯を持っていた。引き抜かれた時の感覚からして鍾離も一度達しているはずだが、熱が引かないのはタルタリヤとて同じだ。からかったら痛い目を見ると知っていたため、それ以上の言及は留めた。
鍾離の手が促すまま、タルタリヤはころりと身体の向きを変える。うつ伏せになって膝を立てれば、自然と腰が持ち上がった。鍾離が足の間に自身の屹立を差し込んで、ゆるゆると前後に動かす。
「そこ、で、いいの」
「息も整わないまま捻じ込むほど鬼ではないからな」
「……お気遣いどうも。っ、正直、それもちょっと、擦れるんだけどさ」
「む。……ああ、そうか。ならまだ少し控えよう」
タルタリヤ自身の裏筋を刺激される羽目になるから、休憩になるかと言われると頷き難いところだ。察した鍾離は動きを止め、そっとその大きな手でタルタリヤの背をなぞった。どうにか鍾離の方を向いたタルタリヤは、その表情を見て唇を噛む。
背中の傷など、正面にある傷よりも恥じるべきものだ。
いくつかは正面から貫通したがために残った痕ではあるものの、一部は背中から食らった攻撃である。それなのに鍾離の眼差しには蔑むような色などなくて、いっそ慈しむといった方がそれらしい。
傷跡に触れる鍾離の手が止まったと同時、鍾離は口を開いた。
「思えば――俺は先ほど答えたし、今度は公子殿の番だな」
「……なんの話?」
あまり良い予感はしない。だが背中に触れる手から意識を逸らせるならばなんでも良かった。問い返せば、鍾離はするりと答える。
「認識票の話だ。あれはスネージナヤの兵たちが持っているものだろう」
千岩軍で認識票が導入されたという話は聞いたことがない。鍾離が認識票の知識を持っているとすれば、人々の噂や他国から輸入された文学作品か何かが元だろう、と思っていた。だからこそ渡したところで意図など気付かないだろうし、探りもしないだろうと考えていた部分があったが、どうやら思った以上に知識はあったらしい。
渡した意図など、問われたところでタルタリヤも明確な答えを持ち合わせていないのだけれど。
「あー……うん、まあ他所については詳しくないけど、俺たちはね」
「又聞き程度にしか知らないから聞きたいんだが、あれは何のために持っているものなんだ?」
スネージナヤの兵とは、即ちファデュイだ。大陸中から募集しているから、スネージナヤ人とは限らない。実際、執行官にも他国出身の者は居る。けれど皆、スネージナヤのために各々の任務を果たすために動いている。
付き纏う悪評を裏付けるように、ファデュイに下る任務は過酷なものが多い。研究員や銀行員などの裏方に回されれば別だが、先遣隊などは過酷な土地を調査しなければならず、その死亡率は言うまでもない。
「存在理由と、しては……死体の身元証明、だね」
「ふむ。ならばやはり他人に渡すものではないな」
「っはぁ……でもあれ、使えないんだよ。もう名前違うし、執行官には、っなんでか、新しいやつを、女皇様がくださらないものだから」
内腿に触れる熱のせいで、どうにも落ち着かない。枕に頭を押し付けながら、タルタリヤは鍾離の問いになんとか答えきった。
執行官入りして以降、新たな認識票が支給されなくなった。執行官としてあちこちへ飛び回るから、所属をいちいち刻みなおしていられないという理由のせいかもしれないが、それならば執行官という地位を刻んでしまえばそれで済むのではないか。
死ななければ良いだけの話だし、タルタリヤは死ぬつもりなど毛頭ないから、他の執行官にも、女皇にさえ支給されない認識票について問いかけたことはなかった。死ななければ良いのだ。そうでなければ、認識票が必要になることもない。
項に生温かい息がかかる。そっと立てられた歯にぴくんと身体が跳ねた。
「だっ、から、見える所はやめろってば」
「つけてない。……事情は、概ね分かった」
噛まれたところをぺろぺろと舐める舌は、まるで懐いた犬のような仕草だった。戯れに交じる触れるだけの口付けが、ひとのかたちをしていることを思い出させる。タルタリヤが解いた鍾離の髪が肩を掠めて、それがくすぐったくて、過敏になった肌には堪えがたかった。
項から口が離れたかと思えば、足で挟んでいた熱が抜けていく。今度は言葉さえなくその切っ先がぬぷぬぷと侵入してきた。
「んぅ、っあ……ぁ、ん」
先ほどまでの悦楽がまだ色濃く残る身体は、鍾離のそれを嬉々として受け入れる。背骨を伝ってせり上がる快楽に嬌声が飛び出て、多少は回っていた思考は途端に霧散した。タルタリヤに覆い被さり、新たに標的にされた項を食む鍾離の唇がそれを更に助長させる。
口付けと舌での愛撫に、歯での刺激を交えながら、鍾離は「公子殿」とタルタリヤを呼んだ。呼びかけに答えてやるには、もうタルタリヤの思考は蕩け始めている。
「――あれは、受け取っておこう」
公子は祖国のため、家族のため、氷神のための駒なのだ。忘却を知らぬ男には余計な世話なのかもしれなかったけれど。
薄っぺらな金属板は最早無意味でしかない、過去の遺物である。そして身につけるために使っていたチェーンは、乱戦の果てに千切れて何度か買い替えていたような安物だった。
それでも、記憶以外の何をも遺してやれない男に対して渡せる、唯一の――タルタリヤの一部だった。
ゆるゆると動き出した鍾離の方を向いて、タルタリヤはその唇に自身の唇を寄せる。
「すきに、していいよ」
一瞬見開かれた目が、す、と細められた。
緩やかな律動が止まり、タルタリヤは溢れる唾液をこくりと飲み込む。
荒い息と嬌声とに混じって消えてしまいそうだった言葉は、しっかりと鍾離の耳に届いたようだった。
「言われなくても、最初からそのつもりだ」
「ぁ、ははっ……なら、よかった」
鍾離の唇がタルタリヤの背に、無数の傷跡に落とされる。
この男はきっと、些細な傷跡一つさえ忘れることはないのだろう。――忘れようとさえ、しないのだろう。
2021.1.26